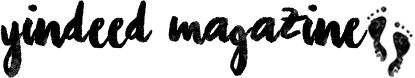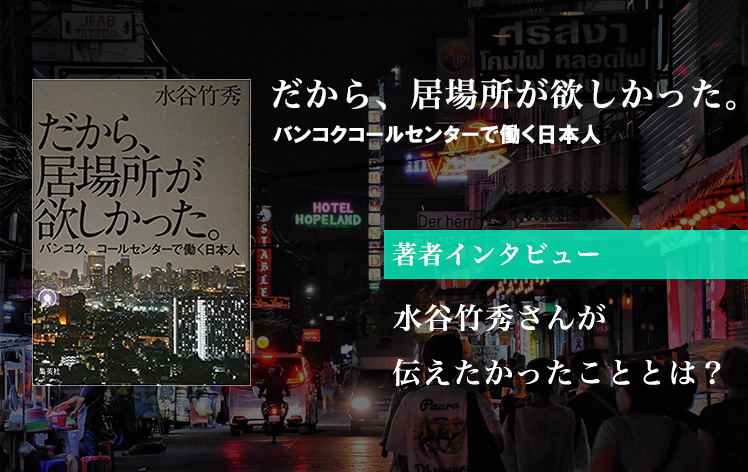去る9月26日、開高健ノンフィクション賞受賞作家、水谷竹秀さんの著作、『だから、居場所が欲しかった。 バンコク、コールセンターで働く日本人(以下、本書)』(集英社)が発売された。バンコクのコールセンターで働く、元非正規労働者、元風俗嬢、夜逃げしてきた家族、男娼の子供を生んだシングルマザーなどを取り上げたノンフィクション作品である。
発売日の翌日には、「月給9万円」タイのコールセンターで働く30代日本人女性の憂鬱という水谷さんが書いた記事が公開された。 この記事は、本書の一部を加筆したもので、「バンコクのコールセンターで働く日本人女性が男娼の子供を身籠り、出産する…」という衝撃的な内容だ。公開直後からSNS上で反響(バズ)を巻き起こし、特にタイ・バンコク在住者の間では大きな話題となった。
水谷さんが本書を通じて伝えたかったことは何なのか?
新刊発売直後の9月末、一時帰国の折に東京で水谷さんにインタビューを行い、本書の執筆に至った動機や取材を通じて感じたことについて話を伺った。
水谷さんとの出会い

インタビューを始める前に、僕と水谷さんの関係を明らかにしておこう。
水谷さんとは僕がタイに移住した翌年、2012年12月に初めてお会いして以来、5年の付き合いになる。
当時、水谷さんは集英社の雑誌『kotoba(コトバ)』で、「若者はアジアを目指す」というテーマで連載を始めるところだった。
ちょうどアジアで現地採用や起業家として働く若者が増えてきた頃で、水谷さんはそんな若者を取材対象としていた。
知人の紹介で水谷さんと知り合い、現地採用として働く1人の若者として、僕もインタビューを受けた。
以来、水谷さんが年に数回取材でタイを訪れるたびに近況報告や情報交換をしている。
本書は2012年から5年の取材期間を経て、書籍化されたものである。
タイトルのとおり、本書の舞台はバンコクのコールセンターだ。僕もタイに移住する前、コールセンターで働くことも考えた。だから本書の登場人物は他人事には思えない。
どんな人が、どんな経緯で、そこで働いているのか?
個人的にとても興味があった。
ここで少し、僕がタイに来た経緯をお話ししたいと思う。
※少しと言いつつ長いので、水谷さんのインタビューをすぐに読みたい人はこちらから。
僕がタイに来た理由

2008年に札幌で撮影
僕はタイに渡る前、2006年〜2011年2月までの間、東京で株式上場関連の会社で営業マンとして働いていた。
入社した2006年はミクシィやグリーが上場した年で、東証マザーズや大証ヘラクレスなどの新興市場が株式市場を牽引し、新規上場社数は188社にも上った。
これは2000年のITバブル(203社)に次ぐ規模で、第二次ITバブル・IPO(新規株式上場)バブルなどと呼ばれ、株式市場は活況を呈していた。
だが2008年、リーマンショックに端を発した世界金融恐慌の影響で株式市場は崩壊。新規上場社数は、2008年49社、2009年19社と、わずか3年で十分の一に激減する。
このタイミングで僕は東京を離れ、札幌支店に転勤した。
札幌では主に道内の上場企業向けに適時開示や株主総会関係書類、IRのコンサルティング業務を行っていた。
そこで、とあるスーパーマーケットチェーンの人事部長から驚くべき話を耳にする。
「札幌市内の店舗で、レジ打ちのパートさんを時給700円で1名募集したところ、50倍もの倍率になった」
というのだ。
リーマンショック後とは言え、東京ではコンビニのアルバイトでも時給1,000円を超える。財政破綻した夕張市など道内の地方であれば分かるが、札幌市内で時給700円で50倍とは…
それまで人生の大半を首都圏で過ごしてきたこともあり、この話には驚きを隠せなかった。
2010年のある出来事が人生を変えた

2011年にソウルにて撮影
2010年8月、2年間の札幌駐在を終え、再び東京本社のIPO営業部に呼び戻された。だが日本市場は上向いているとは言い難く、IPO業界ではアジア市場への上場ブームが起こりつつあった。主に韓国、台湾、香港、シンガポールの新興市場への上場を目指す企業が増えており、「これからはアジア」という風が吹いていたのだ。
東京に戻った直後の2010年9月上旬、東京ビックサイトで開催された「東京ビジネス・サミット2010 」の会場で、“その後の人生を変えた”と言える出来事があった。
「カモメアジア就職」というアジアの求人情報に特化した転職サイトのブースで、同サイトを運営する企業の社長と立ち話をしていた際、こう質問された。
「明石さん、九州全体のハローワークで、正社員求人の平均月給はいくらだと思いますか?」
だいたい15万円くらいかと返答したところ、
「11万円」だと言う。
その社長は続けた。
「一方、上海やバンコクなどアジアにおける現地採用の求人は約15万円〜です」

もはや東南アジアは発展途上国ではなかった 失われた20年を経て、日本は20代の45%が非正規雇用という状況に陥っていた。
2010年の時点で日本の地方都市で働くより、アジアで現地採用として働くほうが多くの収入を得られる時代になっていたのだ。
アジアなら首都とは言え、物価も日本よりは安い。であればアジアで暮らすほうがより人間らしい生活ができるのではないか。1980年生まれの僕は、「日本はアジアNo.1の豊かな国」という意識の中で育ってきたこともあり、その現状に大きな衝撃を受けた。
10年ぶりに訪れたタイで目にしたもの

サイアムパラゴンに衝撃を受けた
この話を聞いてから2週間後、10年ぶりに旅行でタイを訪れる。サイアムやチットロム、スクンビットを歩き回り、タイの著しい経済成長を目の当たりにした。
巨大なデパートに競うように建つ高層ビル、タイの若者の多くがiPhoneを手にし、大戸屋はタイ人で満席だった。バンコクは活気に満ち溢れ、はち切れんばかりのパワーが漲っているように感じられた。
「これがアジアか…」
折しも日本ではアジア上場ブームが巻き起こっていたこともあり、この経済発展の熱気渦巻くバンコクの姿を目にした時、「日本で働いている場合ではない。自分もこの活気の中に身を置きたい」、そう強く思った。
 2006年にオープンしたセントラルワールド当時の僕は30歳という節目の年齢。今後40歳までの10年間をどう生きようかと考えていたところであり、「これからの10年をアジアで生きる」という選択肢は魅力的に映った。というより、もはやそれしか考えられなくなっていた。東南アジアにハマった学生時代から10年を経て、アジア熱が再発してしまったのだ。
2006年にオープンしたセントラルワールド当時の僕は30歳という節目の年齢。今後40歳までの10年間をどう生きようかと考えていたところであり、「これからの10年をアジアで生きる」という選択肢は魅力的に映った。というより、もはやそれしか考えられなくなっていた。東南アジアにハマった学生時代から10年を経て、アジア熱が再発してしまったのだ。
コールセンターが移住の不安を払拭してくれた

タイに着いた初日から3年4ヶ月暮らしたランナム通り
そこで前述の社長の話を思い出した。
これからは間違いなく、より良い暮らしを求めてアジアに出向く日本人の若者が増えるはず。
であれば、日本人向けのサービスや情報発信は今後需要が高まるのではないか。
そこにチャンスがあるかもしれない。
タイ旅行から戻った2ヶ月後には退職届を提出していた。
退職前にはネットでバンコクの求人を探した。タイ語か英語ができれば営業職なら仕事は見つかりそうだった。
それに、「コールセンター」という日本語だけで働ける職場があることも分かった。
性別・年齢・語学力が不問にも関わらずビジネスビザも支給してくれる。
すぐに仕事が決まらなかったとしても、まずはタイ語学校に通いながらコールセンターで働けば生活はしていけるはず。それから転職活動をすればいい。
そう考え、タイへの移住を決断した。
 職場はプラトゥーナム市場近くにあり、活気にあふれていた 結局、タイに渡る直前に知り合った人からの紹介でバンコクの編集プロダクションに就職が決まり、コールセンターで働くことはなかった。
職場はプラトゥーナム市場近くにあり、活気にあふれていた 結局、タイに渡る直前に知り合った人からの紹介でバンコクの編集プロダクションに就職が決まり、コールセンターで働くことはなかった。
だが、何のツテもなくタイに渡る人にとって、コールセンターは移住の不安を払拭してくれる存在であることは間違いない。自分自身の経験からもそう言える。僕にとっても本書のテーマである「バンコクのコールセンターで働く日本人」は、他人事には思えないのだ。
さぁそれでは本題のインタビューを始めよう。
水谷竹秀さんへのインタビュー

著者の水谷竹秀さん
――なぜコールセンターで働く日本人を取材しようと思ったのですか?
水谷:就職氷河期世代や日本社会に馴染めない、希望を持てない若者たちがアジアに向かい、やりがいをみつけて働いている。というところに面白さや希望があると思い、当初はアジアで働く若者、主に現地採用者や起業家を対象に取材を始めました。
若者に話を聞くと、みな前向きで可能性に満ち溢れていた。彼らの中には明るい未来予想図が描かれていたのです。ところが、そこに切迫した問題が感じられなかった。
――2012年前後は、アジアで働く現地採用の若者を取り上げるメディアが増えてきた頃ですよね。
水谷:はい、それもあります。一般的な現地採用者については情報も増え、日本にいる人でも想像できてしまう。
冒頭に出てくるゴーゴーボーイの子供を身籠った女性が、コールセンターの最初の取材対象者だったのですが、その話があまりにも衝撃が大きく、頭から離れなくなってしまったのです。
――僕もバンコクで現地採用として働いていましたが、コールセンター勤務の人に出会うことは滅多にありませんでした。在住者でもコールセンターについては良く知らないという人が多いと思います。
水谷:おっしゃるとおり、バンコクのコールセンターについては実態が知られていなかったのです。
海外就職に関する書籍や記事は数多く世に出ていましたが、海外のコールセンターで働く人々を取り上げた本は見たことがありませんでした。
現地採用の中でもコールセンターはその給料の低さから別枠で語られることが多い。働いている人もコールセンター勤務と明かすことを嫌がる人がほとんどでした。
彼らは決して若くはない30代半ば〜40代の人たち。いわゆる就職氷河期世代です。そこには何か切迫した問題があるはずだという直感が働きました。
1975年生まれの氷河期世代であり、自身もフィリピンで現地採用の記者として長年働いた経験を持つ水谷さん。
本書の登場人物の大半は、水谷さんと同世代である30代後半〜40代。彼らに共感できるところも多かったという。

――水谷さんも現地採用を経験されていますよね。コールセンターで働く人たちが他人事には思えなかった、ということでしょうか?
水谷:過去二作品(『困窮邦人』と『脱出老人』)の取材対象者に比べて、今回は自分と同年代。同じ就職氷河期、失われた20年を生きてきました。まだ結婚もしておらず、将来が確立されていない人が多い。これからどうなるのか不安があるのは自分も同じで、日本に戻ってもやり直しが簡単にできる年齢ではない。そもそも日本社会は一度レールを外れた人間に敗者復活のチャンスを与えない。そんな状況に陥っている彼らの心に寄り添ってみたい、そう思いました。
本書(P.28)で紹介されているとおり、日本で働く単身女性の3人に1人が年収114万円(平均月収9.5万円)に満たない「貧困」という現状。
つまり、日本で非正規労働者として困窮生活を送るより、バンコクのコールセンターで月給3万バーツ(約10万円)で働くほうが、経済的にも精神的にも満たされる可能性が高い。そんな時代を迎えているのだ。
――バンコクのコールセンターは、日本の貧困に対するセイフティーネットという役割を果たしているように見えます。
水谷: 本書のエピローグでもその点には触れましたが、それは海外就職にもかかわらず、それほどの語学力を求められない応募条件が関係しているような気がします。日本社会に息苦しさを感じ、かつて旅したタイで働きたいと思った時に、この条件はとりあえずの就職先になりやすい。それがネットや口コミで広がった結果、セイフティーネットに引っかかるべくした人たちが集まった。だから、コールセンターは日本社会の問題を映し出す鏡のような場所になってしまったのだと理解しています。
本書のキーワードは、「居場所」。水谷さんは、「自分の存在意義を実感することができ、承認欲求を満たせる空間」を居場所と定義する。自身も学生時代、居場所と呼べる心の拠り所は少なかったという。

――僕もその一人かもしれませんが、日本で居場所を見つけられない人が増えているように感じます。それはなぜなのでしょうか?
水谷さん:いつの時代にも居場所を見つけられない人は一定数いるのかなと思います。ただ、僕が特に最近感じるのは、学校でのいじめ、会社内でのパワハラみたいなケースがメディアで表面化していること。 明石さんが「日本で居場所を見つけられない人が増えているように感じる」という感想を持たれるのはそういった背景が関係しているのかもしれません。また、ネット社会のおかげで便利な世の中になったのは確かですが、それによる弊害もある。
ネット社会が産み出した新たな閉塞感といいますか。バンコクに来たからといってそれらがすべて解消されるわけではないと思いますが、それでも居場所を見つけられた人はいる。そんな現実を描くことで、自分の居場所について考えて頂く機会になれば、著者としてこんな嬉しいことはありません。
インタビューは以上。
最後に、本書の中で僕が一番心に残っている一文をご紹介したい。
日本に居場所はなかったかもしれないが、なければないで海外という選択肢がある。他人からは「ただ単に逃げただけじゃないの?」と言われようが、重要なのは本人が生きていることを実感できるかどうかだ。幸せか否かは第三者が決めることではない。(本書 P.54-55)
「幸せとは、居場所を見つけること」
本書を読み、僕はそう受け取った。
「幸せとは何か?」
そのひとつの答えが、本書にある。
それこそが、水谷さんが本書を通して伝えたかったことではないか。
本書に登場する人たちは、失われた20年を経て、閉塞感のある日本では居場所を見つけられず、バンコクに渡った。
そして、ようやくここに居場所を見つけたのだ。
バンコク紀伊国屋書店(伊勢丹店、エムクオーティエ店)でも販売中!